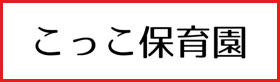ことり保育園の保育方針
ことり保育園のめざす保育
ひよこ会の理念
・自然を感じながら「くう・ねる・あそぶ」を大切に、子どもたちの主体的な育ちを家庭とともに応援します
・保護者、職員、理事など法人運営に関わるすべての人たちが子ども中心につながり合い、安心できる居場所をつくります
・地域の様々な福祉事業をすすめ、みんなで共に暮らせる社会をつくります

各年齢の子ども像
-
5歳児 ・すすんで友だちと遊ぶ子ども ・よく考え作り出す子ども
-
4歳児 ・仲良く遊べる子ども ・何でもやろうとする子ども
-
3歳児 ・よく遊ぶ子ども ・自分のことは、自分でしようとする子ども
-
2歳児 ・友だちの中でのびのびと遊ぶ子ども
-
1歳児 ・見守られていきいきと遊ぶ子ども
-
0歳児 ・みんなに愛されてすこやかに育つ子ども
食の子ども像
- 食欲があり、食べることを楽しむ子どもに
- 自分の健康にとって望ましい物を選んで食べられるように
2025年度(令和7年度) ことり保育園のテーマ
『じぶんが大好き ともだち大好き みんなでつくろう ことり保育園』
ことり保育園は開園し8年目を迎え『くう・ねる・あそぶ』を柱に、今の社会で生きる子どもの姿を丁寧にみつめ、子どもが主体的に自由に暮らす環境と自分らしい自信と思いやりの育つ過程を大切に『子どもが考え自分で決める、どんな思いも大事に育ち合おう』をテーマに保育を積み重ねてきました。子どもたちの育ちをみていると、柔らかでしなやかな心と体を自分のものとし、人や社会と関わり、「自分らしく生きること」をどの年齢の子ども達も楽しんでいると感じます。それは卒園した子どもの姿からも、たくさんの頼もしい話を聞くことができます。子育てとは、どんな子どもに育ってほしいのかでなく、どんな大人へとその子が人生を歩んでいってほしいのか、自分ならきっと大丈夫と自分への信頼を重ね成長していく中で、人生を自分の足で歩んでいく土台を大人と一緒につくる、それがこの6歳までにはとても大切なのです。
 子どもの人生は、生まれた時から子ども自身のものです。赤ちゃんでも子どもは自分の気持ちを持ち生きています。自分の気持ちをよりよく出し発達していくためにも私たち大人は、子どもが安心して思いを伝えることのできる環境と、どの年齢でも子どもが自分で決めていける暮らしを創り、子どもを信じる心の幅を広げながら「子どもが育つ力」を応援していきたいと思います
子どもの人生は、生まれた時から子ども自身のものです。赤ちゃんでも子どもは自分の気持ちを持ち生きています。自分の気持ちをよりよく出し発達していくためにも私たち大人は、子どもが安心して思いを伝えることのできる環境と、どの年齢でも子どもが自分で決めていける暮らしを創り、子どもを信じる心の幅を広げながら「子どもが育つ力」を応援していきたいと思います
〈1・子どもの権利条約をみつめて〉
2023年4月 子ども家庭庁が発足し、子どもの最善の利益を第一に考えた子ども真ん中社会の実現に向け、子ども権利条約に基づき「子ども基本法」が成立しました。これからはこの基本法をもとにして保育・子育てを考えていく時代となりました。ことり保育園は今までも子どもの思いを第一に保育を創ってきましたが、今、この基本法ができたことで、子どもの思いを尊重する保育の土台が明確になったと思います。
〈基本法の4つの柱〉
生きる権利・育つ権利
・「すべての子どもは命が守られ、成長・発達する権利があります」
・「すべての子どもはやりたいことができ、なりたい自分になれる権利があります」
・「すべての子どもたちは皆自分の気持ちを大切にする権利があります」
表現の自由 参加する権利
・「子どもたちは自分の気持ちや感じたことを自由に表し、ものごとに参加する権利があります」 
・「子どもたちは自分のことは自分で決める権利があります」
・「子どもたちは皆自分の好きなことを好きなやり方で、好きな時に、学ぶ権利が あります」
差別の禁止
・「すべての子どもはすべてにおいて差別されず生きる権利があります
子どもの最善の利益を守る権利
・「大人は子どもにとって何が一番大切なのかを考えなければなりません」
ことり保育園 保育方針
・一人ひとりを大切に自分で考えて自分で決めて願いを叶える暮らしを保障します
・子ども、保護者、保育士がつながり、支えあい、思い合い、共に育ちあう園づくりを進めます
・地域の皆様と手をとりあい、子どもの成長をあたたかく見守る保育をめざします
〈一人ひとりを大切に自分で考えて自分で決めて願いを叶える暮らしを保障します〉
 『子ども一人ひとりの願いを叶える保育』『自分で決める』とはどういうことでしょう?それも赤ちゃんの時から?と感じますが、子どもは小さな時からしっかり自分の意志があり、個性やその子らしさがあります。それはまだ言葉を持たない年齢でも、表情や姿から自分のやりたいことを相手に伝え、楽しんでいこうとするのです。それは言い換えれば“自ら発達する” ということなのでしょうね。子ども達は毎日の暮らしの中でいろんなところに自らの足で向かっていきます。その中で窓からのぞいてみえた景色、園庭の草花や虫、石や土、水と出会い、笑って楽しそうにあそぶ大きい子への憧れやけんかしながらも自分の気持ちを一生懸命伝え合っている姿、あやすとあどけなく笑ってくれる小さい子への愛おしさ、子どもにとって心が動くいろんな多くの瞬間、それが子どもの生きる楽しさであり、喜びなのです。新入児の2歳児のK君、毎日どこにいくというぐらい、園内を探索しては遊びをみつけたくさんの子どもや大人と関わり、遊んでいます。休日にどんなテーマパークへつれていくよりもことり保育園に行きたがるそうです。子どもにとって自分でみつけること、自分から関わりにいくことは、思うように自由に動けることはこんなにも子どもの喜びとなっているのだなと感じます。
『子ども一人ひとりの願いを叶える保育』『自分で決める』とはどういうことでしょう?それも赤ちゃんの時から?と感じますが、子どもは小さな時からしっかり自分の意志があり、個性やその子らしさがあります。それはまだ言葉を持たない年齢でも、表情や姿から自分のやりたいことを相手に伝え、楽しんでいこうとするのです。それは言い換えれば“自ら発達する” ということなのでしょうね。子ども達は毎日の暮らしの中でいろんなところに自らの足で向かっていきます。その中で窓からのぞいてみえた景色、園庭の草花や虫、石や土、水と出会い、笑って楽しそうにあそぶ大きい子への憧れやけんかしながらも自分の気持ちを一生懸命伝え合っている姿、あやすとあどけなく笑ってくれる小さい子への愛おしさ、子どもにとって心が動くいろんな多くの瞬間、それが子どもの生きる楽しさであり、喜びなのです。新入児の2歳児のK君、毎日どこにいくというぐらい、園内を探索しては遊びをみつけたくさんの子どもや大人と関わり、遊んでいます。休日にどんなテーマパークへつれていくよりもことり保育園に行きたがるそうです。子どもにとって自分でみつけること、自分から関わりにいくことは、思うように自由に動けることはこんなにも子どもの喜びとなっているのだなと感じます。
毎年、おおたか組はことり最後の一年“おおたかでやりたいこと(例えば海に行く、かなへびをとるなど)”をみんなで考え、それぞれの思いを叶える保育を楽しんでいきます。その願いを叶えるのは子どもたち自身であり、そのための話し合いも楽しみます。そして卒園する頃には彼らの夢は自分たちの手でほとんど叶い、その達成感と満足感で小学校に向かう姿は自信に満ち溢れています。また一人ひとりのやりたいこと仲間と叶え合う日々は、自分の意見を伝え、尊重される実感や、その子らしさを認め合う姿となり、どんな思いもわかり合い、思い合える心となっていくのです。そして人の興味が自分の興味として広がり、「私もやってみよう、やってみたら楽しかった」という意欲へとも繋がっていきます。きっとこの土台こそが、これからの生きる長い人生、自分の夢をもち、夢に向かっていける その子の輝く未来へと繋がっていくのでしょう。
〈子ども、保護者、保育士がつながり、支えあい、思い合い、共に育ちあう園づくりを進めます〉
 開園からことり保育園を創ってきた親が卒園時にこんな言葉を残してくれました。「ことりで子どものやりたい思いを大切にしてもらえた。それと同じように、親の思いも大切に受け止めてもらえた。だからこんな楽しい親子の仲間、つながりが生まれた」と。開園し8年、コロナ化も含め保護者と共に積み上げた『交流会』『ことり盆踊り』『みんなの会』…。今子どもたちのために出来ることは何だろうとおやどりさんが何度も話合い、アイデアを出しながら考えるその姿は「どんな時でもみんなで知恵を出し合えば、乗り越えていける」「人は一人ひとりが違うから素敵であって、思いを表現できるって嬉しいし、みんなでやってみると楽しかった」等、大人もその人らしさを楽しむ大切さをたくさん伝えてくれました。
開園からことり保育園を創ってきた親が卒園時にこんな言葉を残してくれました。「ことりで子どものやりたい思いを大切にしてもらえた。それと同じように、親の思いも大切に受け止めてもらえた。だからこんな楽しい親子の仲間、つながりが生まれた」と。開園し8年、コロナ化も含め保護者と共に積み上げた『交流会』『ことり盆踊り』『みんなの会』…。今子どもたちのために出来ることは何だろうとおやどりさんが何度も話合い、アイデアを出しながら考えるその姿は「どんな時でもみんなで知恵を出し合えば、乗り越えていける」「人は一人ひとりが違うから素敵であって、思いを表現できるって嬉しいし、みんなでやってみると楽しかった」等、大人もその人らしさを楽しむ大切さをたくさん伝えてくれました。
また年3回の奉仕作業では、大人と一緒に子ども達やOB・OGも参加してもらうことも増え、子どもたちはその大人の頑張る姿をみたり聞き、自分も手伝いながら、「僕・私の保育園をみんながきれいにしてくれる」嬉しそうに話しています。プールの組み立て、用水路を掃除、タイヤの山をつくりなど、自分達が遊びやすいように頑張ってくれるお父さん、お母さんたちの姿は、子どもたちに社会貢献やボランティア活動、協力して作業を行うコミュニケーションの大切さなど、たくさんのことを親の背中から学んでいると感じます。本当に毎回たくさんご協力をありがとうございます。今後も懇談会や、行事、交流会、奉仕作業などを通し、人と人が繋がり、安心して生きていける社会を大人の手でつくりを、子どもたちへと伝えていきたいと思います。
 また、保護者から「布おむつ」「薄着」「生活リズム」「子どものいやに付き合っていたらわがままになるのでは」「けんかを大人は止めないの?」「YouTube、ゲームはよくないとわかっていても、子どもがやりたいというから」「読み書きを早く習得しなくていいってどういうこと」「学校で座って授業を受けれるか心配」などの声もきかれます。「学ぶことがたのしい」という好奇心と、姿勢を保つ筋力などしっかり育んでいきたいと思います。
また、保護者から「布おむつ」「薄着」「生活リズム」「子どものいやに付き合っていたらわがままになるのでは」「けんかを大人は止めないの?」「YouTube、ゲームはよくないとわかっていても、子どもがやりたいというから」「読み書きを早く習得しなくていいってどういうこと」「学校で座って授業を受けれるか心配」などの声もきかれます。「学ぶことがたのしい」という好奇心と、姿勢を保つ筋力などしっかり育んでいきたいと思います。
ことりで大切にしている子育てや保育を、今後も保護者と共に学び合っていきたいと思います。
そして、職員も四日市幼児教育センターの研修・全国研修などの実践報告や学び、そして今年度は他園からの見学を積極的に受け入れ、他園見学に行きながらより保育の充実と積み上げを行っていきたいと思います。また今年度は職員の学習会を「食・あそび・環境作り」のグループに分かれて学習を行っていきます。
- ことりの異年齢保育で育つもの

ことりは年齢別クラスで、設定された異年齢保育ではありません。でも子どもは自然に異年齢を求めていきます。違うクラスで給食を食べたり、お昼寝したり、その姿は多様な人との関わりや遊びを求めていくと感じます。その中で、同年齢や異年齢との関係性から育まれる力について職員で考えあってていきたいと思います。
- 環境づくり 「遊びがもっと豊かになり、片づけやすい環境設定とは」
みんなが遊びたくなり、物を大事にしようと思えるような工夫、子どもだけでなくもちろん大人の姿勢も大切。物を大切にする姿は人を大切にする姿へと重なると感じます。
- あそび「先生たちの体験学習」

お散歩、虫や草花、どろんこ遊びの楽しさ、手作りおもちゃ など職員も子ども時代に戻って体験学習や遊びの楽しさ面白さを学んでいきたいと思います。
- 食 食べることはいきること 子どもにとって、人にとって食に楽しさ、大切さを考え合っていきます。
・地域の皆様と手をとりあい、子どもの成長をあたたかく見守る保育をめざします
ことりは住宅街に位置し、お散歩に行くとたくさんの地域の方に見守られている姿を感じます。近隣の方が声をかけてもらいお話したり、ことりの遊ぼう会などに来ていただいたり、コロナ禍前は地域の方も、盆踊りにきてもらい楽しんでもらいました。
現代社会は繋がりがどんどん希薄になり、地域住民が安全、安心して暮らせるまちづくりも少しずつかわりつつあります。しかし、このことりが建つ四郷地区、室山地区は、昔から歴史ある町で、自治会もとてもしっかり動いており、ことりが開園以来、子どもは地域の宝であり、子どもがいる街は地域に元気を与えてくれると、たくさんの力をかして頂きています。道の問題や騒音問題など、地域の方にご迷惑おかけながら、理解して頂いてきました。コロナがあけ、今は、地域のOBやOGが夕方に遊びに来てくれたりと、地域の方から、お花やお野菜を頂いたり繋がりも少しずつ復活してきています。今後も、地域の方々と手をとりあい、「地域こそ我が園庭」と子ども達が安心し過ごせる地域つくりを進めていきたいと思います。
〈 最後に…こどもを真ん中につながろう ~ことりの輪・和・笑~〉
ことり保育園の暮らしをみていると、これから子どもたちが生きていく社会が、ことり保育園のような平和で温かな社会であってほしいと願います。小さい時から外の世界に自分から興味を持ち、楽しみに向かっていく姿。振り返るといつもそこには優しい大人が見守り「いいことみつけたら教えてね 後からいくね。何かあったら帰っておいで」と子どもたちのことを信じ、応援する人の存在。その平和な社会には、憧れがあり、困った時には手を差し伸べてくれる子どもや大人の優しさが溢れている、自分の好きな場所、必要とされる居場所がたくさんあり、その安心の中で、自分で決め、自分でできた、みんなが力をかしてくれた、その達成感や満足感こそが、自己肯定感と他者への信頼と「自分は大事」と思う心をしっかり育んでいくと感じます。そして、それは子どもだけではありません。私たちすべての大人も、同じです。私たちにはそれぞれ生きる価値があり、その価値が大切にされるからこそ社会が豊かになるのです。そんな誰もがその人らしく幸せに生き、支え合い、笑顔ある社会、『輪・和・笑』を大切に、みんなの力で創っていきたいと思います。
子ども達にたくさんの好きな場所があるってすてき
たくさんの安心できる居場所があるって幸せ
イヤイヤ期というけれど 「やるやる期」と呼んであげてもいいのかも
そんな風に子どもを面白がってみていたら なんだか子育てうふふって…笑える時間がふえるかも
≪ことり保育園では各クラスで保育テーマを決め一年間、保育に取り組んでいきます≫
クラス名をクリックする詳しい保育方針がでます
かるがも(0歳児)
『安心を土台に「いろんな”はじめて”をたのしもう』 ~ことりをまるごと好きになろう~
・安心を土台に好きな人・こと・ものを見つけていこう!
・いろいろな発見を、ことりでの生活を子どもも大人も楽しんでいこう!
・食べることを楽しもう
・生活リズムの基礎をつくっていこう
・楽しいこと、おもしろいものをたくさん見つけよう
あひる(1歳児)
『安心できる大人や友だちの中で世界を広げていこう』 ・思いをたっぷり出して自己主張に花を咲かせよう! ・安心できる大人と仲間の中で一人一人の子どもたちが思いを出せように ・沢山の人に見守られ異年齢・同年齢の仲間たちの中で探索活動をたっぷりしよう! ・食べることを楽しもう
すずめ(2歳児)
『心地よいなかまの中で、心のねっこを育てよう』~友達と繋がり世界を拡げよう~ ・友だちの輪をつなげよう ・愛情をいっぱい感じで”自分ってすごい”誇りを大切に! ・安心してできる大人・仲間との生活を土台に生活の居場所を過ごしていこう
ひばり(3歳児)
『すてきなこと、おもしろいことに夢中になって遊ぼう』~イッチョマエを大人も一緒に愉しみましょう~ ・イッチョマエ!の心とともに ・一人ひとりの今を大切に ・子どもたちなりの納得を大切に ・いろんなことを挑戦しよう! ・大人の世界へあこがれが広がるとき、ごっこ遊びの世界も広がる ・会話の花が花開くとき
つばめ(4歳児)
『自分の思いを伝え、自分の世界を広げていこう』~だんなことでもいっぱいやろう・あそぼう・つばめっこ~ ・仲間と共に生活の主人公になろう ・仲間と共にしゃべりこもう・考え合おう ・仲間と共に遊びこもう ・仲間の声をきこう ・命に触れよう 生き物との出会い ・探求心や好奇心を大切にしよう ・つくる・食べる楽しさを味わおう
おおたか(5歳児)
『仲間の中でひとりひとりが自分らしく咲き誇ろう!』~みんなはひとりのためにひとりはみんなのために~ ・話し合う楽しさを感じ、自分の思いを語ろう! ・育ちあえる仲間づくりを通じて、自分もがんばろうとする心を大切に ・自分たちの生活を自分たちで創り出す楽しさを ・クッキングや野菜の栽培を通じて作る楽しさやおいしさを感じよう ・大人同士は大切な子育て仲間… みんなで子どもたちの成長を喜び合おう ・異年齢のかかわりを大切に… 小さい子への関わりで頼られる喜びを