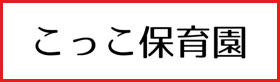ことりの一年
ことり保育園のようす
4月 入園式・進級式
新しいお友だちといっしょに、この1年が楽しく過ごせますように・・・進級した子たちしいクラスになり、成長した自分やお友だち・・・ 期待に胸が大きく膨らみます。
5月 田植え
こっこ保育園の田んぼで田植えをします。お父さん お母さん にもお手伝い頂いて、ひとつひとつ苗を植えていきます。秋には 稲刈りをします。日々の生活ではなかなか知らないことも実体験 することで、成長につながっていきます。
お母さん にもお手伝い頂いて、ひとつひとつ苗を植えていきます。秋には 稲刈りをします。日々の生活ではなかなか知らないことも実体験 することで、成長につながっていきます。
7月 プールあそび・流しそうめん
夏は子どもたちの大好きなプールが始まります。ことり保育園のプールは組み立て式の小さいプールですが、子どもたちは楽しそうです、「先生、みとって~」 顔をつけたり、走り回ったり、泳いだり・・・

楽しそうな子どもたちの歓声が響きます。暑い日は毎日プールで遊びます。子どもたちは大満足、先生はクタクタ・・・
流しそうめんも楽しい行事です。ことり保育園の流しそうめんはきゅうりやトマトも流れてきます。小さい子は手づかみですが、年中さんはフォークで、年長さんになると箸でチャレンジします。使う道具もグレードアップしていきます!子どもたちにとって流れてくるものをつかむのは結構難しいようですが、うまくすくえると、「とれたよ!」と嬉しそう。




8月 なつまつり
保護者会が子どもたちになつまつりを企画してくれました。みんなで簡単おにぎりをつくって、カキ氷、魚つり、うちわつくりを楽しみました。最後はお父さんお母さんもいっしょにみんなで盆踊りを楽しみました。



9月 おおたか組(年長児)キャンプ
毎年、朝明渓谷へキャンプに出かけます。川遊び、カレー作り、ドラム缶 ふろ、夜のおさんぽ・むしとり、花火・・・ 卒園になる子どもたちにとっていい思い出になります。みんなでキャンプをつくることでクラスの結束力もさらに強くなります。保護者にもお手伝いを募り、子どもたちが寝た後は火を囲んで夜遅くまでの2次会・・・ お父さんお母さんたちの結束力も強くなります。
ふろ、夜のおさんぽ・むしとり、花火・・・ 卒園になる子どもたちにとっていい思い出になります。みんなでキャンプをつくることでクラスの結束力もさらに強くなります。保護者にもお手伝いを募り、子どもたちが寝た後は火を囲んで夜遅くまでの2次会・・・ お父さんお母さんたちの結束力も強くなります。

10月 運動会「よーいことりどん」
ことり保育園の運動会は子どもたちの日頃の姿を観て頂くよう、運動会のために練習を積み重ねることは敢えて行いません。大きい子たちは自分たちが日ごろの遊びの中から得意なことを選び、登り棒・なわとび・たけうま・とびばこを披露します。ビデオカメラの撮影もご遠慮いただいて、保護者たちも子どもたちの真剣な姿を実際に目で見て感じて頂いています。沢山のおやどりさん(ことり保育園の保護者のことです)に見守られながら、少しの緊張とやりきった達成感が大きな自信につながっていきます。





11月 収穫祭
5月に植えたお米をいよいよ刈り取り、出来上 がったお米で収穫祭をします。お米は園庭の炊き出しかまどで羽釜で炊き上げます。家庭の炊飯器で炊いたご飯よりもずっとおいしく「おいしいね」「おこげをください」おいしいご飯をみんなで園庭で食べて、子どもたちも違いを十分味わいます。わたしたちも日頃の生活でつい出来合いのものを買ってしまいがちになりますが、お米づくりは八十八の苦労があるといわれることを子どもたちは少し理解してくれることでしょう。
がったお米で収穫祭をします。お米は園庭の炊き出しかまどで羽釜で炊き上げます。家庭の炊飯器で炊いたご飯よりもずっとおいしく「おいしいね」「おこげをください」おいしいご飯をみんなで園庭で食べて、子どもたちも違いを十分味わいます。わたしたちも日頃の生活でつい出来合いのものを買ってしまいがちになりますが、お米づくりは八十八の苦労があるといわれることを子どもたちは少し理解してくれることでしょう。
12月 クリスマス会
12月はこどもたちも楽しみにしているクリス マス会を行います。ことり保育園にはこどもたちから見れば、本物のサンタさんが来てくれるのです・・・(OBの子たちからもあのサンタは誰だったのだろう?と聞かれますが・・・本物のサンタさんなのです)それぞれのクラスにプレゼントをもらってみんな大よろこび・・・コマやけん玉のプレゼントも頂き、コマ名人やけん玉名人が生まれるのです。
マス会を行います。ことり保育園にはこどもたちから見れば、本物のサンタさんが来てくれるのです・・・(OBの子たちからもあのサンタは誰だったのだろう?と聞かれますが・・・本物のサンタさんなのです)それぞれのクラスにプレゼントをもらってみんな大よろこび・・・コマやけん玉のプレゼントも頂き、コマ名人やけん玉名人が生まれるのです。
 1月 おもちつき
1月 おもちつき
おもちつきは最近は身近に見かけることも少なくなりました。うすを用意して、もち米をかまどでせいろで蒸しておもちつきをはじめます。なんども経験しているおおたか組の子たちになるとそんな準備のこともよく知っていてお手伝いもしてくれます。きねでもちをつくにはコツもあります。腰に力を入れて大人顔負けのつき方ができる子もいます。お米を蒸すにおい、ぺったんぺったんはじける音・・・日頃できないことをみんなで体験できることもことり保育園の自慢の行事です。
2月 ことりみんなの会
どこの保育園でもこの時期に発表会があります。ことりみんなの会は運動会と同じ趣旨で、発表会の練習を積むのではなく、日頃の遊びの中からやみんなの好きな絵本のお話から劇あそびを披露します。ひとつの出し物をみんなで力を合わせ取り組むことも大切な経験です。運動会と同じように自分の得意なものを披露する演出もあり、おやどりさんの大きな拍手がホールに響きます。
3月 卒園式
年長のおおたか組の子どもたちが巣立ちする日がいよいよ来ました。「私は〇〇小学校へ行きます」おやどりさんや先生の前で誇らしげに卒園証書を掲げる姿は大きな自信に満ちあふれています。友だちやすべてのおやどりさんや先生に大切に支えられ、心も体も大きく育った彼らは小学校へ行っても、人にやさしく寄り添い、人を深く愛せる子にさらに成長していくことと思います。